

新年の散歩。ひさしぶりにこの辺りを歩いたせいか、写真を撮っていてわりと手応えがあった。去年の夏に引っ越してきてから、よく近所を散歩しながら写真を撮っているけれど、だんだんと似たり寄ったりの写真になってきているような気がしていた。自分の固定化した意識(と未熟な技術)がそうさせるのだと思う。
近所と言ってもそれなりに広い範囲で、そこには写真に写る無数のものがあるわけだし、引いたり寄ったり、フレーミングの仕方も無数にある。季節や時刻や天候や人々の営みなどによっても、空間はその都度多様な現れ方をする。だから理想としては、いつまで経っても撮り尽くすことなく、日々の散歩のなかで延々と撮り続けていけるように写真を撮れるようになれたら、と思う。以下、写真12点。上の2点も含めてすべて撮影順。
■
今年観た(写真を撮った)主な建築。
- クリストファー・アレグザンダー《メゾン・ド・楼蘭》 https://richeamateur.hatenablog.jp/entry/20200720/1595170800
- フランク・ロイド・ライト+遠藤新《自由学園明日館》 https://richeamateur.hatenablog.jp/entry/20200721/1595257200
- 伊東忠太《東京都慰霊堂》 https://richeamateur.hatenablog.jp/entry/20200901/1598886000
- 川崎大師 https://richeamateur.hatenablog.jp/entry/20200913/1599922800
- 大谷幸夫《川崎市河原町高層公営住宅団地》 https://richeamateur.hatenablog.jp/entry/20200914/1600009200
- アンリ・ラパン+宮内省内匠寮《東京都庭園美術館》 https://richeamateur.hatenablog.jp/entry/20200927/1601132400
- 村野藤吾《旧箱根樹木園休憩所》 https://richeamateur.hatenablog.jp/entry/20201025/1603551600
- 同《ザ・プリンス 箱根芦ノ湖》 https://richeamateur.hatenablog.jp/entry/20201026/1603638000
新作を観ない1年だった。
■

近所を散歩して撮った写真。傾斜地の尾根のようなところから。冬の午前中の光。
■
『住宅建築』12月号(10月17日)に寄稿したテキスト「若気のいたりで撮られた写真」を、『住宅建築』編集部の了承も得て、noteで再公開した。写真集『建築のことばを探す 多木浩二の建築写真』(編=飯沼珠実、寄稿=今福龍太、建築の建築、2020年)の書評として書いたもの。
note.com
もともと「この本については何も語らないつもりだった」(7月26日)はずが、いざ書いてみるとやはり多くの人に読んでほしくなる。というか書評を書くだけでは飽き足りず、ネット配信(→)でしゃべるまでになった(そちらでは意図して本書自体にはあまり触れていないけれども)。
この書評が『住宅建築』に載った後、ある近しい人から、「新刊の書評はポジティブにその本の可能性を引き出すべきであって、これは良い書評とは言えない」というようなことを言われた。「批判」を批判する古谷利裕さんの言葉(7月12日)を思い出す。ただ、その人が指摘してくれたことの意味も分からないではないけれど、可能性という言葉を使うなら、僕としてはこの書評では、今回の写真集の批判を通してむしろ多木浩二の建築写真の可能性を開くようなことをしたつもりでいる。批判とは、ある物事の誤りや欠点や限界を指摘することで、別の可能性を開く行為ではないだろうか。多木さんの写真をことさら持ち上げたいわけではないのだけど、今回の写真集の存在によって、その写真やそこに写る建築、多木浩二本人、さらにはそれらをめぐる生きられた歴史が、いいかげんなレッテルで片付けられてしまうのは忍びない。そういう思いが根本にあった。
実際、僕がこの書評でした批判はまったく独創的なものではなく、写真集としてパッケージングされ完結したものに対してそれと符合しない外部の事実を示し、「閉ざされているところ、隠蔽があるところ、一部に限定がなされるようなところ」(2018年7月17日)の風通しを良くしたということだと思っている。
- 追記(2021年1月15日)
■

ヤスパースの『哲学入門』(草薙正夫訳、新潮文庫、1954年)を読みかけのままにしていたら(10月23日)、この12月に『新版 哲学入門』(林田新二訳、リベルタス出版)が出版された。草薙訳とは文体がだいぶ異なるようだけど、この林田訳も新訳ということではないらしい。
付録の「哲学を学ぶひとのために」の訳は、『柳宗悦と民藝の哲学』(2018年7月17日)の大沢啓徳さんが新しく手がけられている。とりあえずその部分を読んでみると、書かれている内容についての評価はできないものの、歴史上の哲学者に対して批判であれ歯に衣着せぬ物言いで客観的価値を断言していく様(その行為が人類全体としての哲学のためになると信じて)に、柳宗悦の文と通じるものを感じる。
ヤスパースは日本の建築分野では白井晟一が戦前のドイツ留学中に師事したということ(だけ)で名前が出てくる。建築ではヤスパースと同時代で近い位置にいたハイデッガーのほうがよく取り上げられるけど、前に大沢さんから、ヤスパースを好む人はハイデッガーを好まずハイデッガーを好む人はヤスパースを好まない傾向があると聞いたのが妙に印象に残っている。
■
Amazonにて、来年5月30日発売予定で、atelier nishikata(小野弘人+西尾玲子)の作品集『Almost, Not』が予約販売されている。
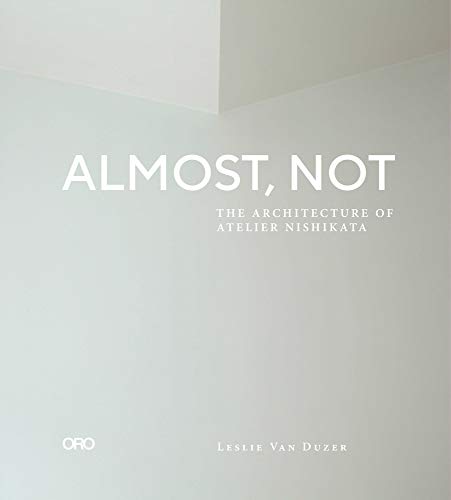
Almost, Not: The Architecture of Atelier Nishikata
- 作者:Van Duzer, Leslie
- 発売日: 2021/05/30
- メディア: ペーパーバック
www.oroeditions.com
■
今年はどこからもカレンダーをもらえる見込みがないので、オンラインの芹沢銈介美術館ミュージアムショップで、卓上版のカレンダーを注文してみた。
seribi-museum.shop-pro.jp
1971年のカレンダーの復刻だから、祝日は自分でチェックする必要がある。まあ、あまり機能的ではないかもしれない。せっかくなので合わせて風呂敷も、手ごろなものを1枚注文した。
『建築と日常』No.5(→)では河井寬次郎の建築の仕事について坂本一成さんにインタヴューをしたけれど、じつは坂本さんが民藝運動の作家のなかで最も作品に共感するのは芹沢銈介だと仰っていた。白井晟一の設計である静岡の芹沢銈介美術館にもいずれ行ってみたい。
■

『NOBODY』2年ちょっと振りの最新号。創刊20年を振り返る特集が組まれている(創刊50号ではなく創刊20年を優先させていることにリアルな何かを感じる)。
過去の総覧には僕や『建築と日常』の名前も載っていた。僕にとって『NOBODY』はほとんどイコール結城さん(『映画空間400選』の共編者)なのだけど、結城さんともずいぶん会っていないし、ついこの前と思っていたあれもこれも、並べてみるともうみんな昔のことになっているのだということを思い知らされた。
以下、2009年の『建築と日常』創刊前夜に『nobody』30号に寄稿したテキスト(誌面PDF)。
- 建築と日常──偶然足を踏み入れた小学校で懐かしい思い出に浸るの巻 https://kentikutonitijou.web.fc2.com/profile/text_nobody30.pdf
以下、これまでにウェブ版に投稿したレビュー4本。
■
以前、SDレビュー2014の展覧会評で、実物が展示できない建築展というものの難しさについて触れたことがあった(→)。その後、このブログでも「日本の家 1945年以降の建築と暮らし」展について書いたなかで建築展のあり方に言及しているけれど(2017年7月24日)、実際の建築展でもうひとつ具体的な問題として挙げられるのは、概して内容が詰め込みすぎになるという点だと思う。訪れた鑑賞者がその場でどういう体験をするのかが度外視され、会場を埋め尽くす情報の量が一方的に優先される。展覧会場で一度に100点の絵画を観ることは可能でも、一度に100点の図面を観て、それらに付随する数千字の解説文を読むことは、一般の人間の能力からして不可能だろう。だからそうした建築展ではいつも過密な情報にくたくたになりながら、しかし出された料理を食べきれずに残してしまうような後ろめたさをもって会場を後にすることになる。
こうした建築展の傾向は、特に過去の建築家を大々的に振り返る企画で顕著になる。そこでは展覧という行為と研究という行為が重ねられていて、もうひとつのアウトプットとして分厚い書籍が同時刊行されたりする。あるいは展覧会という現実の活動が予定されているからこそ、そうした研究や出版が可能になると言ってもよいのかもしれない。それはそれで有意義で貴重な機会に違いなく、それぞれの関係者には晴れの舞台のために力を尽くしてもらえたらよいと思う。ただ、そういう機会を活かすなかで、研究と展覧の性質の違いや書籍と展覧会の性質の違いをしっかりと見定め、よりよい建築展のあり方を考えられないものだろうか。他でもない建築の展覧会で、その空間における人間の体験がないがしろにされているというのは憂うべきことだと思う(ただし、森美術館「建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの」(2018年5月15日)のように、観客に対してアトラクティブであることを目指しても別の問題が発生しうる。また例えば森美術館のような一般の美術館と、研究機関でもある国立近現代建築資料館のような施設とでは、建築展のあり方も自ずと変わってくると思う)。
■

自分には撮れなさそうなタイプの写真がiPhoneのカメラアプリで撮れた。本当は右と上を若干トリミングしたいところだけど、iPhoneで撮った写真はなんとなく構図をいじらないようにしている。日付を入れているのはその縛りでもある。
横浜赤レンガ倉庫1号館で「建築家 浦辺鎮太郎の仕事 横浜展──都市デザインへの挑戦」(〜12/13)、BankARTの2会場で「M meets M 村野藤吾展 槇文彦展」(〜12/27)を観た。
■
アッバス・キアロスタミの『トラベラー』(1974)と『ホームワーク』(1989)をブルーレイで観た。『トラベラー』は長編デビュー作として驚くほど完成度が高い。ただ、キアロスタミ特有のマジックのような詩性はあまり感じられず、ネオレアリズモを思わせるストレートでシビアな作品。この画面にみなぎる緊張感を巧みに解いていったのが後の作品と言えるかもしれない。
『ホームワーク』は一転してレトリカルな作品。ドキュメンタリーの制作主体を透明なものとせず(撮影対象の側からのカメラでやたらと見返される)、対象となる子供たちも、登校時の無垢的な子供、集会時の社会的な子供、そして薄暗い部屋で取り調べのようにカメラの前にさらされた個としての子供と、3つの様態を写す。そのことで映画を一元的な安定したパースペクティブに収束させず、当時のイランの教育や社会の状況をありありと浮かび上がらせるとともに、より普遍的なレベルでの子供というものの存在を照らし出す。
「大人になったらパイロットになりたい」と言う子供に、インタビュアーであるキアロスタミが「なぜ?」と問うと、「サダム(フセイン)を殺すため」という答え。それに対して「君が大人になる前にサダムが死んだら?」とさらに問い、あらためて考え込む子供──。
■
noteに「思い出すことは何か」(約4000字)をアップした。編集を担当した『建築のポートレート』(写真・文=香山壽夫、LIXIL出版、2017年)の巻末に「編集者あとがき」として掲載された文章で、香山先生の写真を解説しつつ、建築家が撮影した建築写真について論じている。LIXIL出版の廃業によって、いずれ『建築のポートレート』(→)も手に入りづらくなると思うので、今のうちに興味を持ってもらえたらありがたい。
note.com
「思い出すことは何か」では香山先生が若い頃に撮った建築写真について、その建築の意味をあらかじめ理解して構図を決めたというより、「若者の直感によってまず撮影され、その写真が事後的に、若者に建築家としてのまなざしを与えた」のではないかと書いた。この「理解が先か写真が先か」問題は、この前の「多木浩二と建築写真──三人寄れば文殊の知恵」(→)でも取り沙汰された(が話はあまり深められていない気がする)。多木浩二の建築写真は、一般の記録的な建築写真に比べれば明らかに、写真が事後的に意味を生成するところがあると思う。しかし一方で、建築の写真を撮るにはまず建築を見なければならず、多木さんにとって見ることは読むことでもあっただろうから、知性の導きなく感性の趣くまま撮ったとも考えにくい。実際の写真の主なものを見ても、なんの知的な見通しもないまま撮れる写真ではないように思える。それに比べると香山先生の写真はより保守的で、日常に根ざしている。
■
昨日は原美術館の後、岡﨑乾二郎さんのふたつの展覧会「TOPICA PICTUS てんのうず」Takuro Someya Contemporary Art(〜12/12)と「TOPICA PICTUS きょうばし」南天子画廊(〜12/12)をハシゴし、さらに日本橋髙島屋の美術画廊Xで「海へ還る──緒方敏明展」(〜12/7)を観た。



岡﨑さんの〈ゼロ・サムネイル〉シリーズは、それが十数年前に作られ始めた頃には、キャンバスとして最小の単位を用いることで美術の高度な専門的文脈から離れた「そのもの」(色、形、それらの組み合わせ)としての魅力が迫ってくるような印象があったのだけど(僕には)、ここ数年の岡﨑さんにおける歴史への積極的な言及や『抽象の力』(亜紀書房、2018年)などの仕事を経て、〈ゼロ・サムネイル〉の小さな作品群がじつは美術の歴史の網の目のなかに深く組み込まれていることが浮かび上がってきた。岡﨑さんにとっては最初から当然のごとくそういうものだったのかもしれないけど、今の岩波のウェブ連載(→)やいくつかの展覧会場で掲示ないし配布されているプリントによって、〈TOPICA PICTUS〉ではそうした関係性のありよう(制作した絵とテキストと参照された作品の「三体問題」)が実際にテキストで表現されるようになってきている。とはいえ作品がそのように歴史的なネットワークの中にあることと、作品がそこに「そのもの」としてあることとは、決して矛盾するわけではないのだろうとも思う。あるいはむしろ作品が「そのもの」としてあるからこそ、歴史的なネットワークにも確かに存在しうると言えるだろうか。






「海へ還る──緒方敏明展」は陶芸による作品群。未知の作家だったけれど、たまたまネットで展覧会のことを目にして訪れてみた。会場に掲げられた舟越桂による短文「緒方君の建物を飛ぶ」で書かれているとおり、ミニチュアとして想像的に身を置くことができる空間性を備えているように思われる。ファンタジー性の強いかたちもあるけれど、シンプルな外形のものは1970年代に坂本一成さんがつくっていた建築やその模型、あるいは当時の文章を思い起こさせる。
それは単に家の形をしていたにすぎない。かといって具体的な形を思い出すこともできないのだが。町の一画にひどくあたりまえに、穏やかに、そしてそこにあることに疑いをもたせない何気なさのなかにあった。一見素朴でありながら、粗野というわけでなく、むしろ洗練されているかに見えた。それはその町の片隅のまわりの家々から必ずしも際立ってはいなかったが、埋没しているわけでもなかった。[…]どこかにこの家はあった。私の生まれた町の一隅にあったかも知れない。いやもしかしたら幼い時の絵本の1ページにあったのかも。あるいは旅の汽車から下りた小さな町での家かも。いやそんな遠くでなくともこの町のどこかにもその家はありそうなのだが。こんな記憶の家があなたにもないだろうか。
- 坂本一成「家形を思い、求めて」『坂本一成 住宅─日常の詩学』TOTO出版、2001年(初出:『新建築』1979年2月号)
原美術館とTakuro Someya Contemporary Artは同じ品川区内で意外と近く(それぞれの場所の地域性はかなり異なる)、写真を撮りながら歩いて移動したのだけど、帰宅して数日後、一眼レフで撮ったそれらの写真をうっかり削除してしまった。iPhoneと一眼レフを併用することで起こったミス。街のかたちも面白く、けっこういい感触で撮っていたので残念だ。
■

先日(9月27日)のリベンジであらためて原美術館を訪れ、「光―呼吸 時をすくう5人」展を観た(〜1/11、要予約)。どの作家の作品も現実的な空間に想像的な時空が重ねられているという点で共通するのではないかと思う。それは原美術館(旧原邸、設計=渡辺仁、1938年竣工)という現実の空間の最後の展覧会であることと響き合うような気がした。
どれも見応えがあったなかで、特に佐藤雅晴の《東京尾行》(2016)が印象深い。動画作品が展覧会場で流されていると「YouTubeでいいじゃん」と思ってしまいがちだけど、これは原美術館の現実の空間で観る意味がある(出展作は下のYouTube版よりずっと長いというか多い)。
短い断片が集合した映像なのでどこから観始めてもストレスがないという展示上のメリットも大きいけれど、YouTubeだと鑑賞者自身が作品世界をその都度ゼロからスタートさせるのに対し、展覧会場では散在する複数のモニターでそれぞれの断片がエンドレスに流され続け、自分と関係なく存在する多様な世界の印象をもたらす。そして実写+アニメによって現実と想像の時空を重ねるような作品のあり方は、(自らの私性に覆われた私室で観るよりも)さまざまな歴史や文脈をたたえたこの空間に身を置いて観ることで、鑑賞者自身もその作品世界に反響し混じり合うような効果を強める気がする。
1階の会場全体に流れていた無人ピアノの演奏(ドビュッシー「月の光」)は、空間的に断片化された作品世界を音によって統合する機能をもつ。無人でありながら鍵盤が動いて音楽が演奏され続けるピアノは、「ここではないどこか」を想像させる装置として、それ自体が現実と想像の時空を重ねる作品の一部であり、またかつて住宅だった(裕福な一家の洋風の邸宅で当時からピアノが置かれていたかもしれないと思わせる)原美術館の空間とも響き合う重要な要素になっていた。
実写の一部をアニメに差し替えるという手法自体はきっとだいぶ昔からあるだろうし、コマーシャルに使われそうな大衆性も感じさせるものの、作品としての切り取り方や完成のさせ方がよいのだろうと思う。そうした手法の単純さや原始性、大衆性が作品の力になっている。アニメ化された部分のほうにむしろ生き生きしたものが感じられる(そしてそれが周囲の環境や背景も活性化させる)という経験は、抽象という行為の意味や人間の認識の仕方、世界のあり方を考えさせる。

